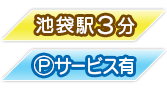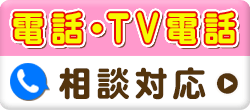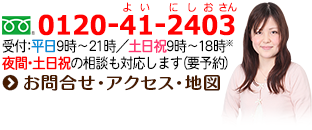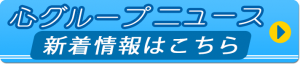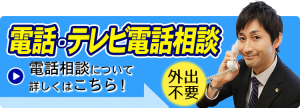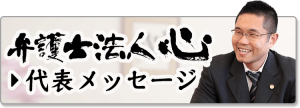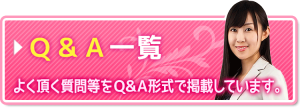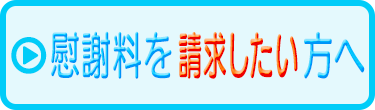不倫慰謝料を請求できる条件
不貞行為による慰謝料請求は、民法709条「不法行為に基づく損害賠償」を根拠に請求することになります。そのため、請求が認められるためには、民法709条の要件を満たすことが必要になります。
関連条文
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
1 故意・過失
⑴ 故意
故意とは、自分の行為が他人の権利や利益を侵害し損害を発生させることを認識しながら、これを容認してそれを実行することを言います。
不貞行為の場合で言うと、不貞相手が既婚者であることを知りながら、肉体関係を持つことを言います。
ここで「既婚者であることを知りながら」とは、一般的に「不貞相手に配偶者がいることを知っている」ことで足りるとされています。
言い換えると、「相手方が未婚だと信じていた」「相手方は婚姻歴があるが既に離婚しており現在は独身だと信じていた」といったケースでは故意が否定される場合があります(但し、後述する「過失」の点は問題として残ります)。
それでは、不貞行為の慰謝料請求をするにあたっての「肉体関係」とは何を指すのでしょうか。
ここで言う「肉体関係」とは基本的に性交渉を指しています。
そのため、「配偶者が異性と食事に行っていた」「配偶者が異性と遊園地に行っていた」といったことだけでは「肉体関係」がないので不貞行為に当たらないことになります。
また、頻繁にメールやSNSでやり取りをする行為も同様に不貞行為には当たりません。
キスまで至っていても、一般的には不貞行為と認定されることは容易でありません。
⑵ 過失
過失とは、一定の事実を認識することができるはずなのに、不注意で認識しなかったことを言います。
不貞行為の場合で言うと、不貞相手が既婚者であることを気付けたにもかかわらず不注意によって既婚者と気付かず肉体関係を持ってしまったことを言います。
「不貞相手が既婚者であることを知らなかった」となれば故意は否定されますが、次に出てくるのがこの過失です。「不貞相手が既婚者であることを知らなかった」ことに不注意があったのではないか、一般人の注意力をもってすれば当然気付けたのではないか、ということが問われるわけです。
ここで、「たしかに不貞相手が既婚者であることは知らなかったのだろうが、一般人の注意力をもってすれば不貞相手が既婚者であったと気付けたはずだ」と認定されますと「過失がある」となり、不貞行為による慰謝料請求を受けることになります。
不貞の相手方から「もう夫婦関係は破綻したと言っていた」「既に離婚したと言っていた」という主張が出ることもありますが、一般的にはこのような主張のみによって「過失がない」と裁判所が認めることはなかなかありません。
肉体関係を持つくらいに親密な関係である以上、過失があると捉えられてしまうことが多いのです。
一方、過去の裁判例では、通常は独身者のみが参加するお見合いパーティーで知り合った相手方が氏名・住所等も偽った上で独身だと詐称していたケースで過失なしと判断したものもあります。
故意がなくても過失が認められれば慰謝料請求は認められることとなりますが、一般的に故意がある場合よりは賠償額が軽減される要素にはなります。
2 権利の侵害と損害の発生
慰謝料請求も損害賠償請求の一種です。
そのため、不貞行為による慰謝料請求では何が「損害」であるかも重要になります。
不貞行為とは、夫婦間の婚姻生活の破壊を招く可能性のある行為ですので、その結果としての「損害」とは「円満な夫婦間の婚姻生活が悪化したこと、あるいは離婚に至ったことによる精神的苦痛」ということになります。
典型的な例が、「不貞行為前は夫婦関係が円満だったにもかかわらず、不貞行為が原因で離婚に至った」というケースです。
夫婦円満という状況から離婚という著しい落差が精神的な苦痛ということになり慰謝料を請求できることになるわけです。
もっとも、このように不貞行為前の夫婦関係が円満であったことが必須というわけではありません。
夫婦関係がやや疎遠、あるいは希薄であったところ、不貞行為が原因で離婚に至ったという場合も慰謝料を請求できます。
ただし、円満な状態であった時と比べて慰謝料額が減額されることが一般的です。
一方、不貞行為の前から既に夫婦関係が破綻していた場合には、守るべき「夫婦間の婚姻生活」が当初から存在していなかったことになります。
そのため、既に夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求は認められないことになります。
3 時効
ここまで述べた、不貞行為による慰謝料請求が認められる要件を満たしたとしても、その後長期間請求を怠っていると請求が認められなくなることがあります。
それが「時効(消滅時効)」です。
関連条文
民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
このように、不貞行為による慰謝料請求は不貞の事実及び不貞行為の相手方を知ってから3年を経過すると、時効により慰謝料請求が認められなくなるということになります。
では、「3年」の時効がスタートはいつになるのでしょうか。
ポイントとなるのは「損害及び加害者を知った時」の意味です。
⑴ 加害者を知った時
「加害者を知った時」とは、加害者の住所・氏名を知った時とされています(最判昭和48年11月16日)。
加害者の住所・氏名が分かれば、一般的に慰謝料の請求も可能になるからです。
⑵ 損害を知った時
不貞に基づく慰謝料請求も「不貞によってどのような精神的損害を被ったか」によって分類されます。
① 不貞行為自体から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料請求
この請求の場合は「不貞行為の事実を知った時」から時効がスタートすることになります。
② 不貞行為による婚姻関係破綻から発生する精神的な苦痛に対する慰謝料請求
この請求の場合は「不貞行為によって婚姻関係が破綻した時」から時効がスタートすることになります。
③ 不貞行為により離婚に至ったことから発生する精神的な苦痛に対する慰謝料請求
この請求の場合は「不貞行為により離婚した時」から時効がスタートすることになります。
⑶ 時効の完成を止めるためには
いったんスタートした時効を止めるためには裁判や調停を起こすことが最も確実です。
内容証明等を使って督促をすることも有効ですが、時効を止める効果は一時的なものでしかありません。